不動産投資に興味を持たれる方は数多くいます。しかし、様々な事情で興味を持つところで終わってしまい、実際の不動産投資を断念される方もいらっしゃいます。
その中でも、「自分は公務員だから不動産投資をすることはできない」というケースがみられます。
確かに公務員には副業は禁止されていますが、不動産投資のような不労所得もまた禁じられているのでしょうか?
そこで今回は、公務員が副業を禁止されている理由や、公務員が不労所得のために不動産投資を行う際の前提条件、公務員が不労所得を狙って不動産投資をするメリット、そして公務員が不労所得を得る活動をする際の注意点について、解説していきます。
【議題】公務員が不労所得を得ることは違法?
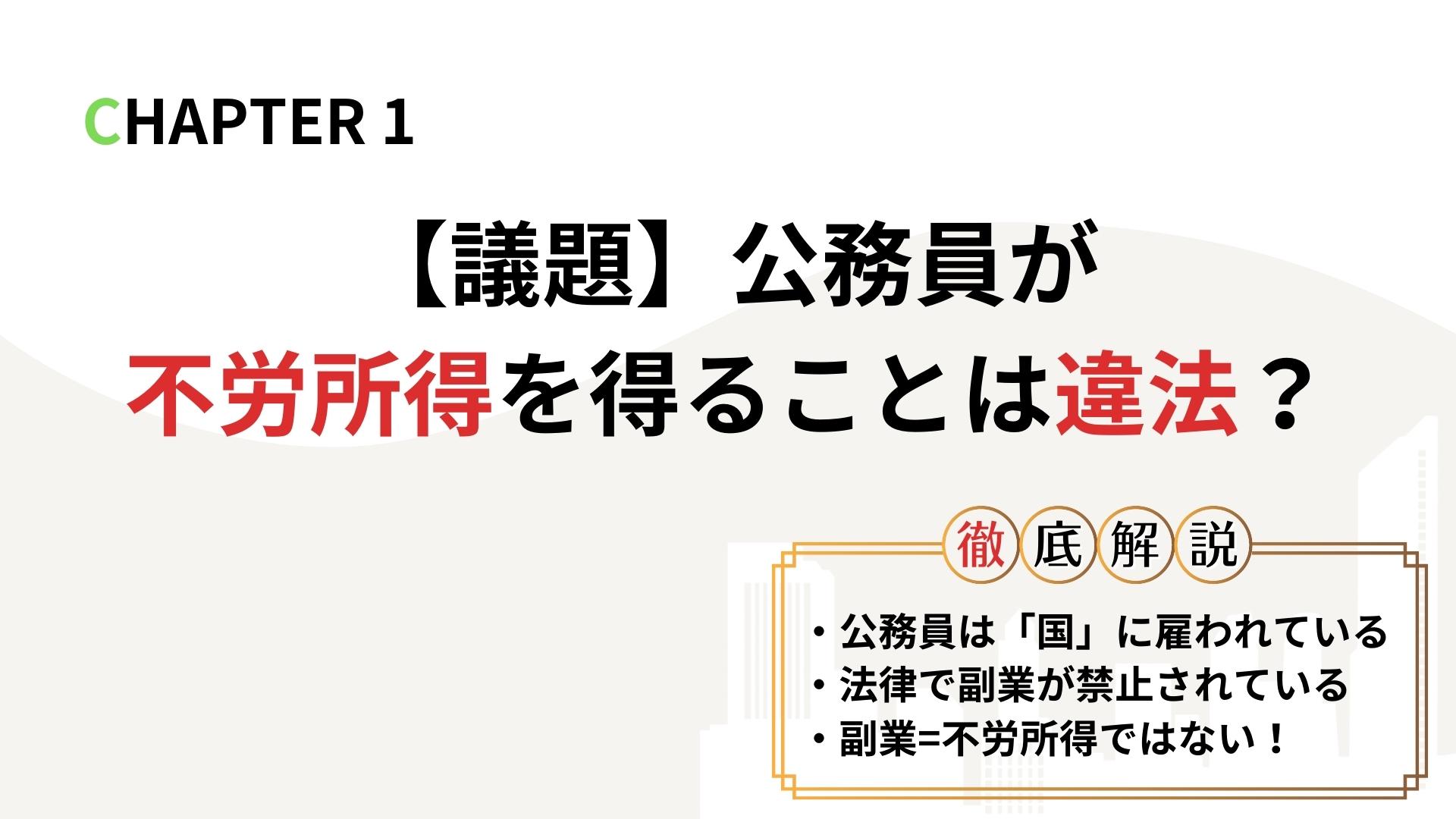
「公務員」は「国」に雇われている立場のため、民間のために働くことに集中すべきであるという考えがあります。こうしたところから原則、公務員は副業を禁止されています。
しかし、公務員の不労所得については、特に禁じる法令法規はありません。「副業禁止=不労所得禁止」と勘違いされるきらいがありますが、副業と不労所得はそもそも別物ということを頭に入れておきましょう。
公務員も不労所得を得てよいのです!
公務員が副業を禁止されるのはなぜ?
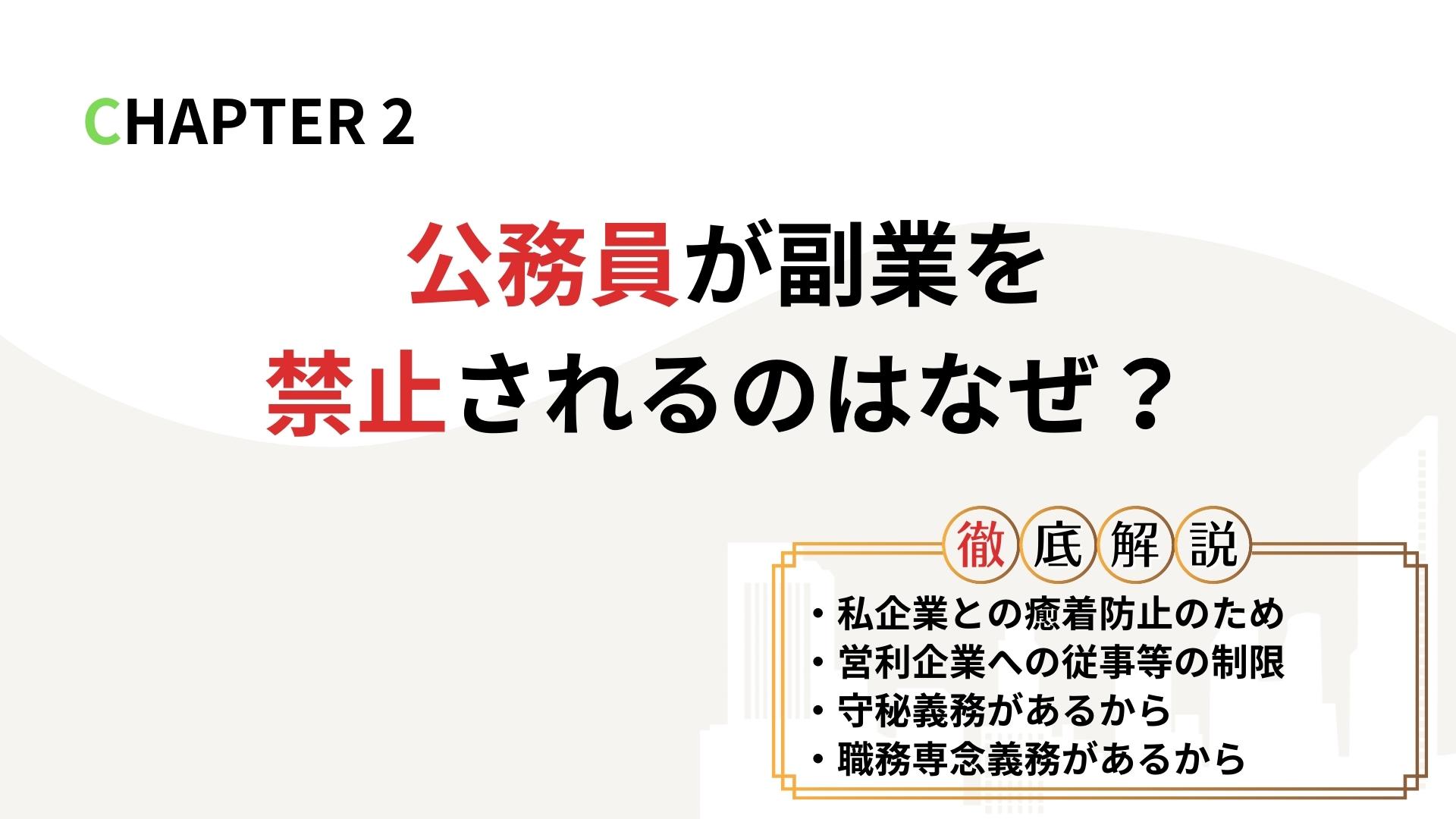
では、どうして公務員は副業を禁じられることが多いのでしょうか。この理由は主に以下の5つが挙げられるでしょう。
法律や内規等で定められているものを含めて、解説していきます。
私企業との癒着防止のため
民間企業は利益を追求する組織であり、そこに公務員が関わることで、何らかのいわゆる「公務員パワー」を使った見返りを求められる可能性があります。
そうなると、その見返りを目当てに不適切な行為が行われる可能性が出てくる、というわけです。具体的には、賄賂の要求や便宜供与の強要などが想定されます。
よって、公務員には副業を禁止している、という観点も考えられます。
営利企業への従事等の制限
そもそも「営利企業」とは何か?という疑問を持つ人もいるかもしれません。
営利企業とは簡単に説明すると、営利を目的として営む企業のことです。つまり、国内ほぼ全ての会社がこれに該当することになります。
例えば、飲食店であれば「客に料理を提供する」ことを対価として金銭を得ていることになりますので、営利企業の最たるものと言えます。
「国家公務員法」などでは、公務員はこうした「営利を目的とする企業、団体」に属さないように規定されています。
守秘義務があるから
公務員は「公務上の秘密を守る義務」を負っています。よって、仮に「機密事項を漏洩した場合の罰則規定」があった場合、最悪、懲戒免職処分を受ける可能性もあります。
副業で本業の関連職種に就いた場合、どうしても守秘義務を守り通すことが難しいケースも想定されます。
よって、公務員は副業を行うこと自体が難しいと言えるでしょう。
職務専念義務があるから
「公務員は、勤務時間及びその職務上の注意力のすべてを職責遂行のために使うべき」といった主旨のことが、「国公法第101条」には明記されています。
副業の中にはスキマ時間で取り組めるものもあります。しかし、キマ時間でも勤務時間中にかわりはありません。加えて、勤務時間中に副業関係の連絡があれば、これに応答することで本来の仕事に支障が出る場合もあります。
そういったことから「職務専念義務」の観点からも副業を禁じるのが一般的である、というわけです。
公務員が不労所得のために不動産投資を行う際の前提条件
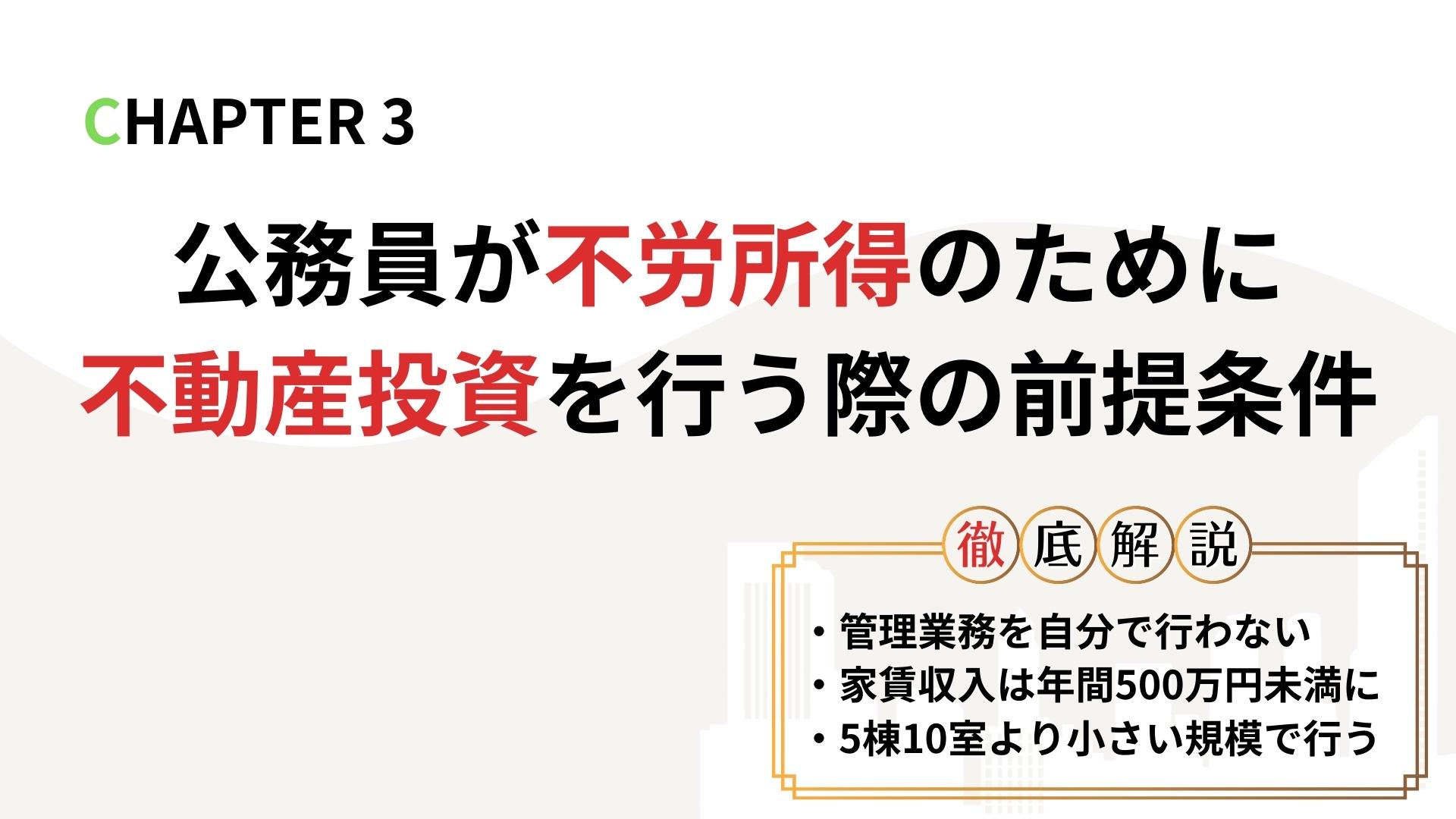
そもそも、公務員が不労所得を得るために活動すること自体は副業には当たらないという考え方もできます。
では、不動産投資を不労所得を得るための活動の一環として行う場合、どういった前提条件が満たされる必要があるのでしょうか。ここではこれについてみていきます。
管理業務を自分で行わない
そもそも不動産投資における管理業務は、「業務」というくらいですから、公務員がこうしたものに取り組む場合、管理実務にタッチすると「不労」所得ではなくなります。
副業禁止規定にも抵触する恐れが出てくるでしょう。
よって「管理業務は不動産投資会社に任せっきり」というところまで持っていきたいものです。
家賃収入は年間500万円未満に抑える
家賃収入は、年間500万円未満に収めることが望ましいと言えます。
そのためには、シンプルに考えれば部屋数を落とすか、家賃を落とすかになります。おすすめしたいのは部屋数を落とし、家賃はきちんと徴収することです。
部屋数は今後の職業の状況に応じて変動させられますが、家賃は一度落とすと更新タイミング(通常2年)まで戻すことは難しいからです。
5棟10室より小さい規模で行う
不動産投資を「5棟10室」より小さい規模で行うことは、副業としてみなされないための、ほぼ絶対条件と言って良いです。
すなわち4棟9室ならセーフというわけです。この数値に留意しましょう。
公務員が不労所得を狙って不動産投資をするメリット
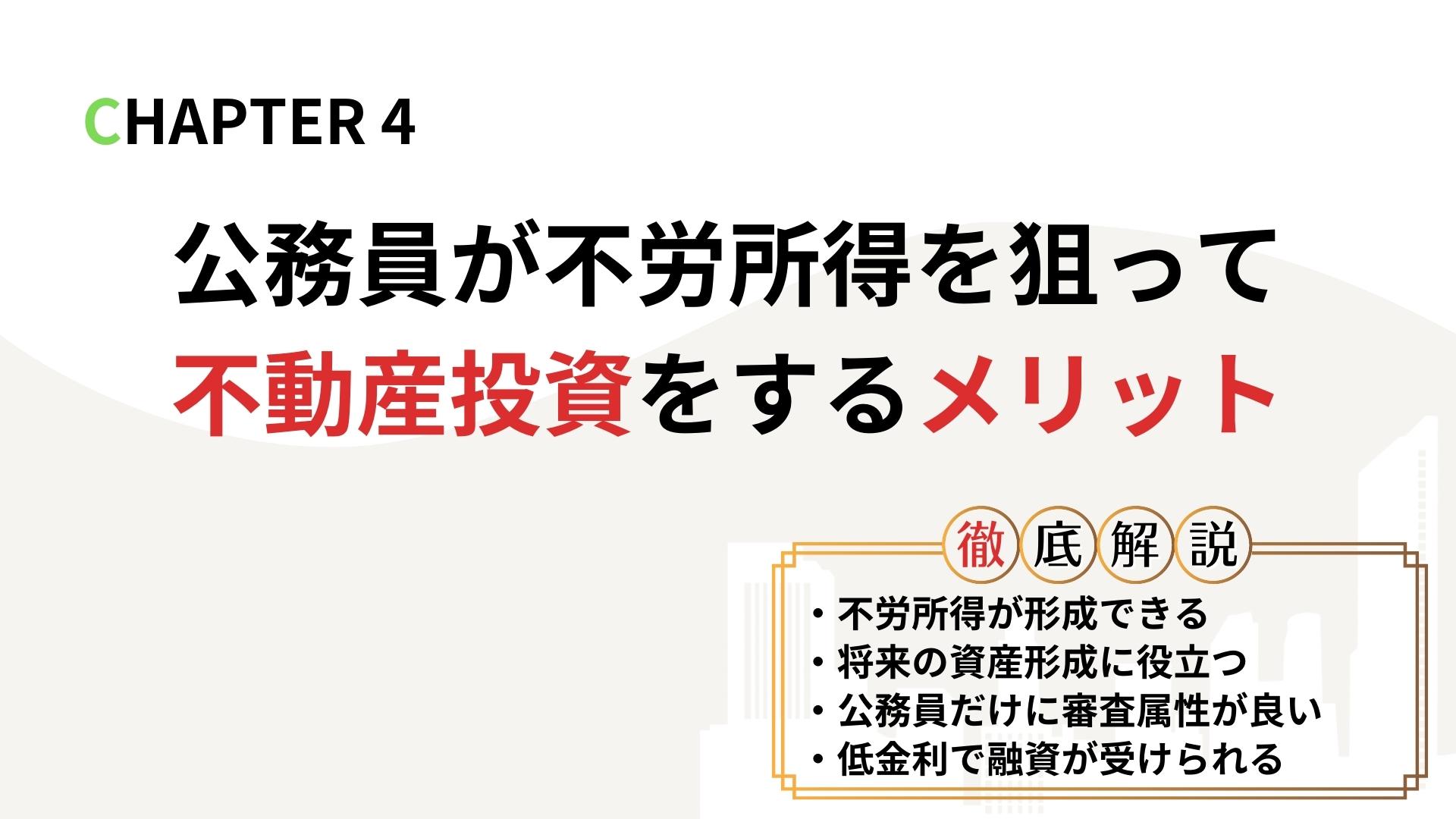
不動産投資は「安定的な収入源」となり得るものです。また「将来の資産形成」につながることも大きなメリットと言えます。
そこでここでは、公務員が不労所得を狙って不動産投資をするメリットを紹介していきます。
不労所得が形成できる
不労所得が形成できるというのは、不動産投資の大きな魅力のひとつです。
それも公務員という安定した職業のキャリアに就いているうちにこうした取り組みが出来ることで、今後の将来にわたって安定して不動産投資を続けていくことができるでしょう。
将来の資産形成に役立つ
不動産投資は、長期的な視点で見ると非常に優れた資産運用方法であり、公務員のような安定性のある身分の場合は特に有効といえるでしょう。
特に公務員は老後の生活資金の確保という点では不安が残ることもあります。不動産投資はこうした問題に対して有効な手段となるのです。
公務員だけに審査属性が良い
公務員は今や、金融関係の審査において最も有利なステータスを持っているといっても過言ではありません。
それは「公務員」というだけで「信用度が高い」からです。公務員は企業における倒産リスクもありえず、高い安定性があります。それゆえに、不動産投資の審査においても有利になるのです。
属性が良い分、低金利で融資が受けられる
上で述べた通り、公務員は金融審査上の属性が極めて良好なため、ローン会社・銀行等からの借入がしやすくなります。
また、公務員が不動産投資を行う場合、通常よりも低い利率で借り入れができることが多いのも特徴です。
公務員が不労所得を得る活動をする際の注意点
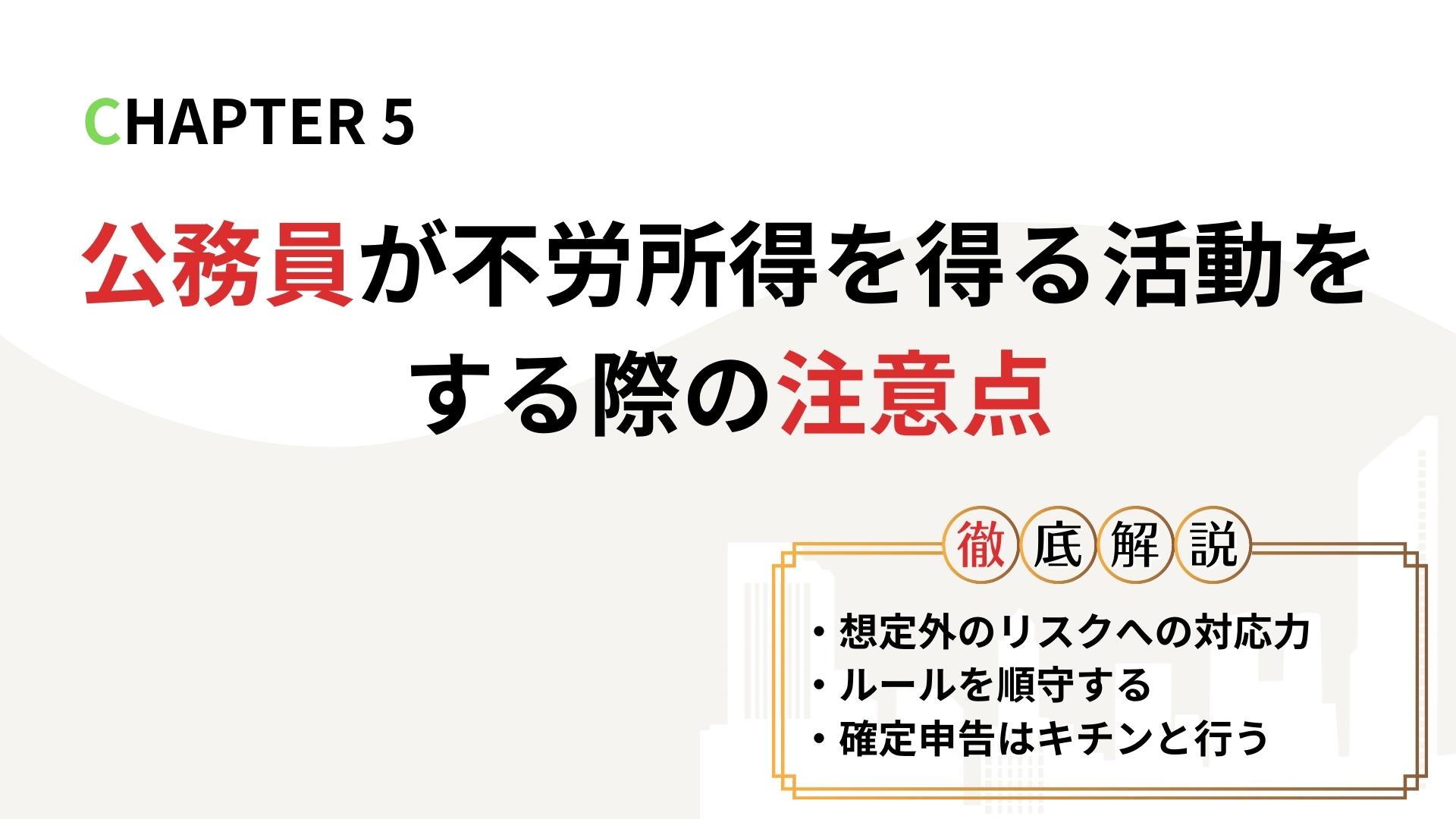
公務員が不労所得を得ようとする場合、以下の3つのポイントに注意しなければいけません。以下、順をおって解説していきます。
想定外のリスクに対応出来る余力を残しておく
例えば、物件において想定外の災害や事故が起こった場合に、資金力の観点から対処できないような状況になってしまえば本末転倒です。
火災保険や地震保険に加入しておくことや、修繕積立金を毎月積み立てておくことなどが、リスク対応として考えられます。その他、自己資金をある程度残しておくことも重要です。
これは不動産の種類によって異なります。ワンルームマンションであればほぼいらないですし、一棟アパートであれば多少(できれば30~100万円ほど)は必要になります。
ルールを遵守する
公務員としての本分を守ることはもちろん、不動産投資のルールについてもしっかり把握しておく必要があります。
不動産投資は、「投資」というだけあってお金を動かすことになるものです。そのため、不動産投資はルールを遵守する必要があります。
不動産投資会社が仲介してくれるとはいえ、基本的には本人が契約主体となる取引になるため、ルールを理解し、遵守することが何より大切になってきます。
また、不動産投資は「投資」という性質上、不動産投資会社の営業マンに丸め込まれてしまうケースも多くみられます。本当の意味でルールを遵守する営業マンとの付き合いを見つけていくこともまた、重要なポイントとなるでしょう。
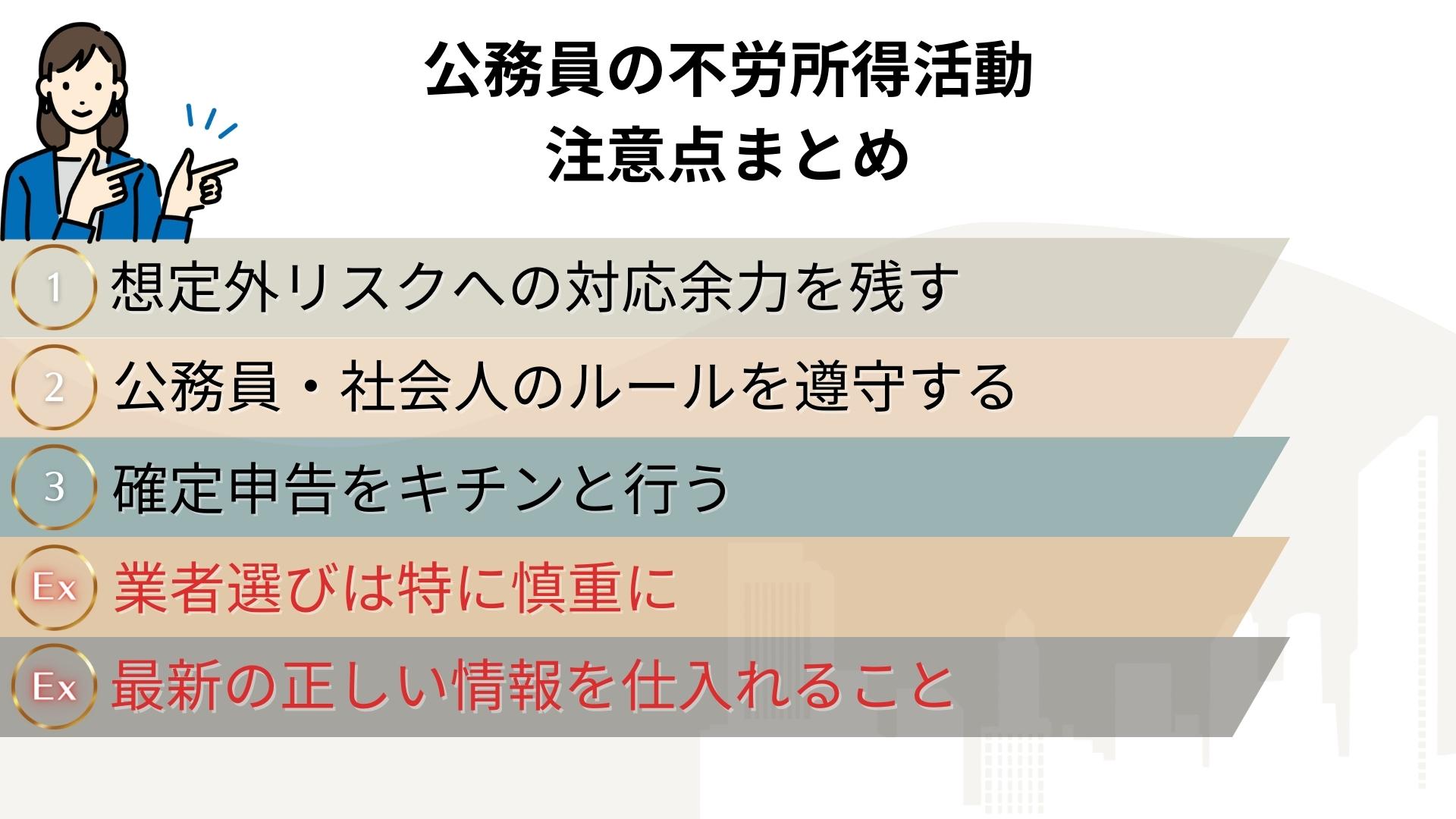
確定申告はキチンと行う
これは不動産投資に限らず、投資全般に言えることですが、税金はしっかりと納めなければいけません。
これらを怠ってしまうと、脱税とみなされてペナルティを受けかねません。もし納税が遅れてしまった場合は延滞金が発生してしまいます。
まとめ
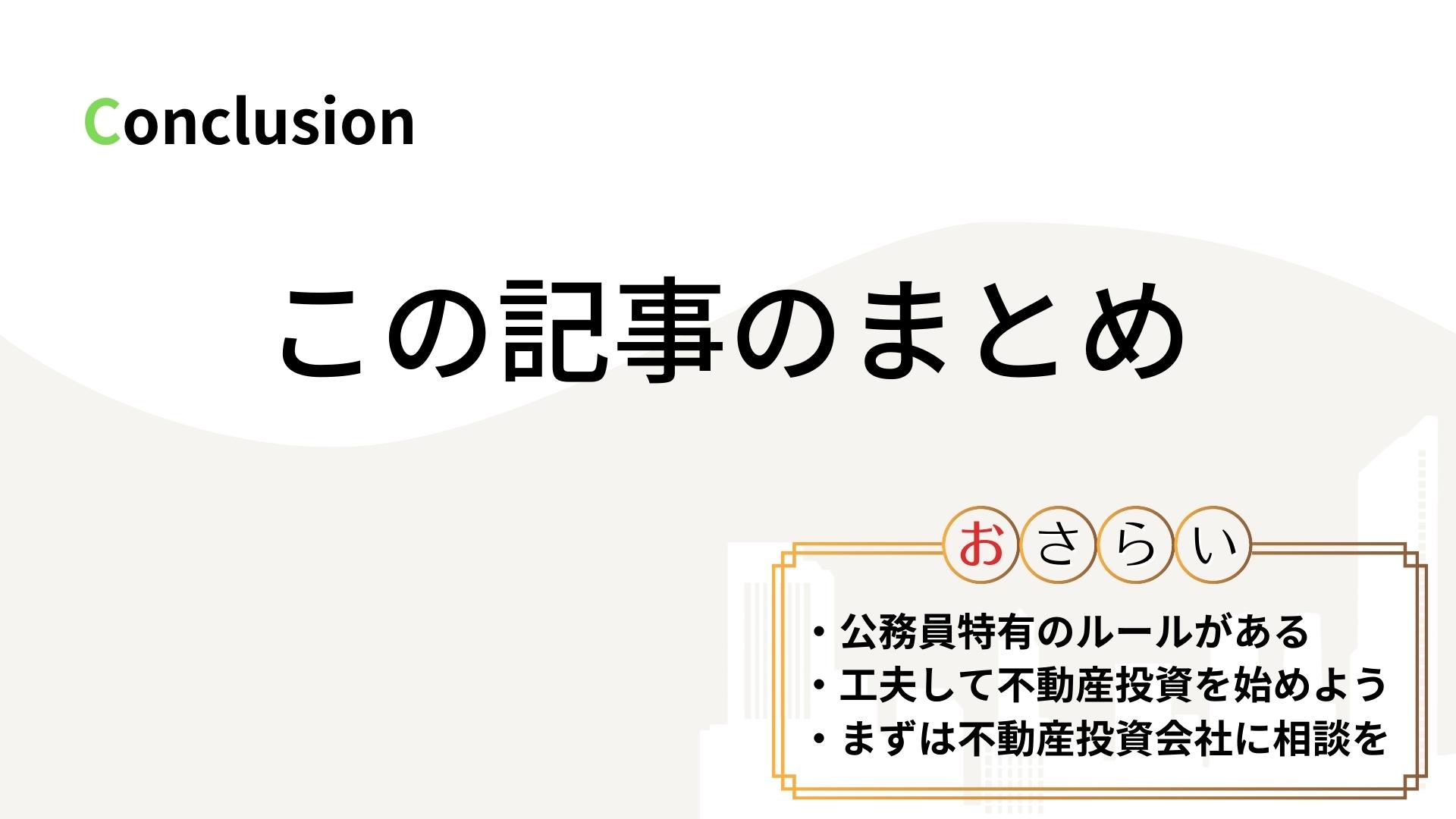
今回は、公務員が副業を禁止されている理由や、公務員が不労所得のために不動産投資を行う際の前提条件、公務員が不労所得を狙って不動産投資をするメリット、そして公務員が不労所得を得る活動をする際の注意点について、解説してきました。
公務員には、自営業を営む人や民間企業に勤めている人とは違った、公務員特有のルールがあります。それを守ることはとても大切です。
しかし、ルールを守った上で、工夫をすることでできることは数多くあります。不動産投資もその一つです。
どのようにすれば自分もまた不動産投資に取り組むことができるのか、一度信頼のおける不動産投資会社に相談してみるのも、一つの手ではないでしょうか。

